先々週に続いて、今度はカミさんと、GW後半に2泊で長野に行ってきた。
去年の夏も妙高から戸隠、栂池と旅をしたのだが、なんでまた行ったかというと、その時にメインの行き先にしていた「奥裾花自然園」が、ないことにアプローチ道路の工事で夏季期間休園していて行けないという大計画ミスをやらかしたそのリベンジのためと、娘がまだ3歳の28年前のGWに戸隠に行った時のビデオをその夏旅から帰ってきてから観たら、一面に水芭蕉が咲いている映像があり、こんなにすごかったっけ、もう一度見たいね、という話になった、ということでね。
なので今回は、去年も行った「戸隠森林植物園」と「奥裾花自然園」に水芭蕉を見に行くのをメインの目的に、あとは「奥裾花自然園」の手前にあるこれも去年通った鬼無里(きなさ・現在は村ではなく長野市の一部の地区の名称)の里山散策をしたり、「長野県立美術館」に併設されている、カミさんの好きな画家東山魁夷から作品や関係書籍の寄贈を受けたという「東山魁夷館」、あと何度も近くには来ているのに行ったことがなかった「善光寺」に行く計画を立てた。
3日の朝8時すぎに車で出発したが、この日の関越の混雑はひどかった。いつもなら混んでも東松山インターあたりまでなのに、事故も絡んで、上信越道の分岐までずっとに加え、上信越道の吉井インターまで、平均時速20kmほどの大渋滞。予定では長野の信濃町インターを降りてから昼食にするはずが、ずっと手前の佐久PAでそばを食い、「戸隠森林植物園」に着いた時は2時間ほど押して3時すぎになっていた。
「戸隠森林植物園」は"水芭蕉園"とか"水芭蕉の小径"とか名付けられた場所があちこちにあるのだが、以前に行った時のビデオに較べると、今年は開花が遅くなっているのか、それほど「一面に」という感じの咲き方ではなかったな。まぁでも水の流れに沿って湿地帯に咲く水芭蕉(冒頭の写真ね)は可憐だ。ただあの白い部分は実際には花びらではなく葉が変化したもので、「苞(ほう)」と呼ばれるらしいんだけどね。
一通り植物園の中を歩き戻って来た時にはもう4時半ごろになっていたので、この日は美術館や「善光寺」に行くのは諦めて、今回の宿、長野駅前にあるビジネスホテル「ドーミーイン長野」に向かい、休日はホテル前の道が通行止めのため近くの提携駐車場に停める。ここは夕食は外に食べに行く必要があるし価格はちょっと高めだが、温泉大浴場もあり、コーヒーもタダで飲めるし、その他のサービス面では全く問題ないきれいな宿だ。
長野駅前付近の夕食処は事前に調べておいたが、食べログ高得点のところもそうでないところも、この連休は飛び込みだと入れないところばかりで、1日目は苦労してチェーンの居酒屋を見つけたが、2日目は予約を入れておいた。2日目のそば居酒屋「もみじ茶屋」は、味はよかったが、入り口近くのカウンター席だったため、しょっちゅう飛び込み客が来てほとんどがその都度断られる、その戸の開け閉めでけっこう寒かった。
4日はまずコンビニで昼食のおにぎり他を買い、車で「奥裾花自然園」に向かう。去年ここでナビが暴走してルートを誤ったのだが、それは「自然園」への道路が通行止めだったためらしく、今回はすんなり、とは言え相当な山道を延々と登って、10時半ごろに「奥裾花観光センター」に着く。
ここからはシャトルバスに乗って自然園入口まで行き、5分ほど歩くと「平成の森広場」というところに着くのだが、そこから先はなんと、ほとんどの道が雪に覆われている。雪解け水を踏んでもいい靴が必要だとは認識していたが、こりゃアイゼンが要るレベルだ。帰りのシャトルバスの運ちゃんに訊いたら、今年は特に雪が多いと。これでもあと2,3週もすれば融けると思うけど、とのこと。木道の上か見分けがつかないような危険な場所では、自然園の職員さんが一生懸命雪かきをしていた。
何度も足を滑らせながら「今池湿原」というところまで行くと、おお、ここの尾瀬より本数が多く本州一と言われる水芭蕉はなかなか見事だ。ただここも、例年のピークは5月中旬だそうで、まだちょっと早かったのかな?途中雪のない木道を歩ける場所では、この群落にかなり近づける。
もう1ヶ所の「こうみ平湿原」にも水芭蕉がたくさん咲いていたが、こちらは雪がより深く、あまり近くまでは行けなかった。またその先、「ブナ原生林」も散策するつもりだったのだが、雪が深すぎて通行止めになっており、予定を2時間ほど巻いて自然園入口まで戻って来た。カミさんは水芭蕉が見えるところでおにぎりを食べようと言ったが、これじゃレジャーシート敷いてもお尻が冷たいし寒いし無理でしょ、てことで、「観光センター」まで戻って車の中でおにぎりを食べた。
それから長野市内に戻り、どこの駐車場もかなりの車の列ができていたがその1つに何とか停めて、「県立美術館」と「東山魁夷館」を観に行く。2020年に竣工したという大変モダンでオシャレな建物だ。「県立美術館」の常設展示は大したことはなかったが、ここではちょうど「鈴木敏夫とジブリ展」というのをやっており、時間指定予約制とのことだが15:30の回なら入れるというので、それを予約して「東山魁夷館」に行く。
ここでは東山魁夷が唐招提寺御影堂障壁画制作のため中国を取材して描いたというたくさんのスケッチ--といってもカラーのものも水墨画もある--を中心に展示していてかなり見応えがある。カミさんは東山魁夷の絶筆になったという「夕星」という絵が気に入って、この絵が印刷されたクリアフォルダとかその他いくつか自分へのお土産を買った。
「鈴木敏夫とジブリ展」も、鈴木敏夫氏が徳間書店の編集者からどういう経緯でスタジオジブリの代表になったかとか、各ジブリ映画の製作工程をかなり詳しく展示していて、これまたとても見応えがある。ここは時間指定予約でありながらかなり混雑しており、展示はじっくり時間をかけて観たが、最後のショップはレジに長蛇の列ができていてとてもゆっくり選んだりする気にならなかったので、夕方5時前に隣の「善光寺」に向かった。
初めて行った「善光寺本堂(国宝)」はとても大きくて荘厳な造りで、さすが「牛にひかれて善光寺参り」という、よいことの例えとなる慣用句になるだけのことはある。境内にはお守りやおみくじの自販機があり、ちょっとびっくりした。本堂で例によって家族一同の健康と幸せを祈ってから、重要文化財の山門--5時を過ぎており内部観覧はできなかった--から参道を逆にたどって行ったが、もう遅いので店も半分くらい閉まっていた。
ここの参道にはやはりソフトクリーム屋とかりんごスイーツ屋とかが多くできていたが、愛知の犬山城の参道ほどちゃらちゃらした感じにはなってなかったな。カミさんが家の湯のみが欠けているので買い替えたいと言って探したが、仏具的なのはあってもそういう陶器を売っている店はなかった。
4日の午前中までは雲が多めだったところ雲1つない晴れになった5日は、前日同様「奥裾花自然園」への道をたどり、途中の鬼無里の「鬼無里ふるさと資料館」の向かい側の駐車場に車を停める。「ふるさと資料館」で鬼無里の伝統や歴史の展示を観て、この地に伝わる「鬼女紅葉伝説」を勉強する。
それから駐車場脇にある「そば処鬼無里」で電動レンタサイクルを借り、「白髯神社」とかその他、予め調べておいたビューポイントを巡って行く。鬼無里の里が見下ろせる場所や、白馬~栂池の麓の谷との間の山地の向こうに、去年の夏あれほど見たくても雲に隠れてなかなか見えなかった後立山連峰の雪化粧した山頂稜線が、見事に見える場所があった。
裾花川に沿ってぐるっと里山を周って行って、途中ぼくが速く走りすぎて、カミさんとはぐれちゃって怒られたりしながら、近くのお堂などを巡って、最後に「松厳寺」に行く。ここは本堂が立派で天井絵が見事だったが、ここにあるという「鬼女紅葉」の墓は探してもなかなか見つからず、最後に山門の外に小さな石塔のようなのがあってこれが墓だとわかった。さすが鬼女、ずいぶんと虐げられた扱いだったんだね。
「そば処鬼無里」に自転車を返して、ここで十割そばを食べ、他にも寄る予定の場所はあったが車が混みそうなんで、ホテルに戻って忘れもの--カードキースイッチに挿しといたキャッシュカード。レコーダーで録画するんで部屋出る時にいちいち電源が落ちちゃ困るのでね--を回収してから、9時前ごろに家に帰って来た。帰りの渋滞は行きほどひどくはなかったが、それでも6時間近くかかったかな?鬼無里で買ったおやきを2つずつ車の中で食べたらけっこうお腹いっぱいになり、カミさんはもう何も食べず、ぼくは帰ってからお茶漬け1杯だけ食べた。
てことで今回はまぁまぁ天気に恵まれ、また少し日焼けし、100%果たせなかったけど去年夏の失敗をほとんどリベンジできた、なかなか気持ちのよい初夏旅になりました。
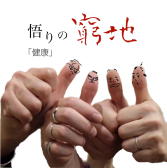


コメント