昨日夜23時ごろに無事帰って来た五島旅行の、今回は2日目と3日目の記録です。2日目と3日目は福江島内をレンタカーで巡る旅。いつもの一人旅書式で、計画旅程を最初に書いてから補足する形で行きますね。
2日目は概ね島の北半分のポイントを巡って行くプランだ。残念ながらこの日は朝から雨。それほど激しくはなかったが、午後に向けて--海辺に行ったからかもだけど--風も強まり、暴風雨の様相を呈してきた。特に午後は景色が美しい場所をたくさん組み込んでいたんだけどなぁ。うーん。
福江島は大ザックリ言えば20Km四方ほどの島なので、車で30~40分も走れば、島を横切ることができる。もっとも一部の海岸線や古い町中などは、道がめちゃ細くて対向車が来たら完全にアウトだったり、石垣塀に両側を擦らないかビクビクするような場所も多いので、道選びを間違えるとそうは行かないんだけどね。
ニッポンレンタカーのお姉さんは地図を示して、こことここは道が細くてくねくね曲がってるので行かない方がいいですよ、と言ってくれたのだが、その2ヶ所とも行程に組み込んであったので、無視して行くことにした。ワインディングロードは大好物なのでね。もっとも今回のHONDA FITはそれほどパワーはないので、そういう場所の運転もそんなに楽しくはないんだけど。
「堂崎教会」は下五島(福江島、久賀島、奈留島とその周辺の島々)でいちばん古い教会で、今は内部がキリシタン弾圧などの歴史を展示する資料館になっている。まず基礎情報を頭に入れる一環として最初に行くことにした。入館料(300円)を取られたのは、前日に行った「五島観光歴史資料館」とここと、最終日に行った「山本二三美術館」だけだった。
ここの展示はそれほど大したことはないのだが、江戸時代初期に徳川幕府の弾圧を受け、島原や天草などから五島に移住して隠れキリシタンとなった信者たちが、キリスト教とバレないように観音様が赤ん坊を抱いた「マリア観音」を崇拝していた、その像などがたくさん置かれている。
ちなみに江戸末期、プティジャン神父により彼らは「信徒発見」されたが、その後明治政府によりさらに厳しい弾圧(「五島崩れ」)を受け、そのことが西欧諸国から激しく非難されて、不平等条約改正の障害になったため、明治6年にやっと、1614年以来259年ぶりにキリスト教信仰が解禁された。
これにより隠れキリシタンたちは、多くがカトリックに合流したが、一部は自分たちのそれまでの秘教形態を捨てられず、そのままのやり方を続けた。近年では彼らを「隠れキリシタン」と言い、最初に偽装棄教した人々のことは「潜伏キリシタン」と呼んで区別することも多いらしい。
次に行った「ドンドン渕」は、どこが道だかわからない森を5分ほど歩いていくとたどり着ける、ちょっとした岩滝のような場所なのだが、高低差数メートルで、大したものではない。夏になるとここの滝壺で、子供たちが水遊びをするそうだ。
「楠原教会」は下五島で2番目に古い教会で、「堂崎教会」に続いてレンガ造りの風情ある建物だった。多くの教会は中に入れて、会衆席の手前までは入れるものの、写真撮影は禁止、というのがほとんどだったが、一部は祭壇の手前まで行けたり、逆にこの「楠原教会」のように鍵がかかっていて中に入れないところもあった。
次の「城岳展望所」は、島北部の半島や島々の美しい景色が望めるはずだったが、この時点でだいぶ雨が激しくなっており、景色も霞んでほとんど見えなかったので、展望所からさらに3分ほど登ると頂上まで行けるようだったが、諦めて早々に引き上げてきた。
「巖立神社」は格式が高いとされる「五島四社」の1つで、五島藩主が最初に建て、600年の歴史があるという。ここは参道の県文化財になっている原生林に、オガタマノキやナタオレノキなど常緑広葉樹が多く繁っており、南国らしい風情と鳥居、立派な本堂という取り合わせが目新しい。
「水ノ浦教会」は大きな木造・白亜の美しい建物で、天気がよくて空が青かったらコントラストがきれいだっただろうなぁと、この日の天気が恨めしく思われた。
それから五島で唯一の道の駅、「遣唐使ふるさと館」内のレストランで昼食にし、土産物屋で家に飾る用に「バラモン凧」の小さいのや、カミさんへの土産に「五島椿茶」、地焼酎などを買う。
次に向かった「高崎鼻」は、島の北西側の「三井楽(みいらく)半島」の東端の出っ張りで、ここから西端の「長崎鼻」までは国の名勝に指定され日本遺産にもなっていて、ここは海に突き出した崖上の草原が美しいはずなのだが、この天気にこんなところを散策するもんじゃない。横殴りの雨に、ここまで持っていたジーパンが完全にずぶ濡れになってしまった。
「三井楽教会」は比較的新しくモダンな作りで、モザイク模様の外壁と、内部のステンドグラスがきれいだった。ちなみに今回も、中に入れなかったところを除くすべての教会、神社、寺で、オフクロから孫まで家族みんなの健康と幸せを祈ったので、多少は霊験あるといいな。
次にまた海辺に出て、空海が書物に残したという言葉「辞本涯」(日本を去る果ての地)を掘った碑が建てられているのを見、そこから海岸沿いの車1台がギリギリ走れるオレンジロードという道を走り、この辺りに移住してきたキリスト教徒の墓が集まった「渕ノ元カトリック墓碑群」を見て、「三井楽長崎鼻灯台」まで行ったが、天気がよかったらこの道はサイコーだったはずなんだけどなぁ。
ここから車で島の東海岸まで移動し、「南河原展望所」に行く予定だったが、もはや景色はほとんど期待できなかったのでそのまま素通りし、「樫ノ浦アコウ巨木」を見に行く。根回り15mもあり、アコウは気根が垂れ下がって支柱根になる木で南国風情があったが、やっぱ雨だとイマイチだったなぁ。
ということでこの日は予定を30分ほど巻いて宿に戻り、冷えた体を風呂で温めて、時間があったので前回のブログを書けた、ってわけでね。この日の写真はロクなのがないので、どんな場所かは上記の旅程のリンクから見てくださいね。
既に長くなってるけど3日目も書いておきますね。朝方残った霧雨が上がり、曇りから午後にはやっと晴れてきたこの日の計画旅程は、福江島のおおむね南半分を周る以下のプラン。
「明星院」と「大宝寺」はいずれも遣唐使として唐に渡った空海に関わる日本遺産で、前者は空海が唐からの帰路に立ち寄り、後に五島藩主の祈願寺になった。18世紀に建てられた現在の本堂は、五島最古の木造建築と言われ、格子天井に狩野永徳の弟子が描いたという花鳥画はなかなか観ごたえがある。
「大宝寺」は701年に創建されたと伝えられる五島最古の寺で、空海がこの付近に漂着し、日本で初めて真言密教の講釈を行ったとされ、これにより寺は真言宗に改宗して、西の高野山と呼ばれるようになった。本殿には最澄が寄進した観音像があるとのことだが、奥まった場所にありよく見えなかった。
「貝津教会」は小ぶりの木造教会で、中から見たステンドグラスが色鮮やかで美しい。
「魚籃観音展望台」は、高浜海水浴場の横に突き出た岬の断崖の上に、航海の安全を祈願して建てられたという観音像の周りから見える海水浴場のエメラルドグリーンの海の色がとてもきれいだ。この時点ではまだ曇り空だったが、晴れていたらさらに素晴らしかっただろうなぁ。
こんなとこ入って行くの?といううねうね道を通り抜けた先の海沿いにある「白鳥神社」は、「五島四社」で2番目に古い神社で、古くは最澄から、明治時代には伊藤博文、大山巌などが参詣したという。鳥居をくぐって階段を登り振り返ると、玉之浦湾の景色が素晴らしい。
「井持浦教会」はレンガ造りに見えるもののかつて台風で倒壊したため今はコンクリート造りになっているということだが、ここは日本初の「ルルド」(奇跡の泉・詳細は上記リンクから)が造られた地とのことで、本場の霊水を注いだここの湧水を信仰する人は全国にいるらしく、ぼくが見に行った時にも、ペットボトルを持って水を汲みに来ているおばさんがいた。
この近辺で1軒だけのドライブインのようなところで昼食にし、次の「玉之浦教会」は街の風景に溶け込んだ風情がよいというので、車を降りずに車内からちょっと眺め、「大山祇(おおやまずみ)神社」に行く。ここは神社自体は小規模なのだが、その参道の上を、アコウの巨木と支柱根が跨って、その間をくぐって行くようになっているのが珍しい。この辺でようやく陽射しが出てきた。
この日事実上最後に行ったのは福江島の西端にある「大瀬崎灯台」だ。ここは駐車場から灯台まで標高差200mほどを延々と下って行かないと到達できず、行き20分、帰り40分と表示がある。この旅最大の難行苦行だ。
別に灯台まで行かなくても、駐車場からちょっと登ったところにある展望台からの景色で十分きれいなのだが、行ってみることに。展望台には人影が見えたが、往復の間、観光客らしい人には1人も会わなかったので、行ってみようって方が奇特なのかな?やっと着いても灯台そばの断崖の景色が見れるくらいのことだしね。
汗だくになって灯台から戻り、展望台まで登ってみると、外海側の景色もさることながら、反対側の玉之浦(半島が細く伸びて本島との間に入り込んだ入江)の景観が本当に素晴らしかった(冒頭の写真ね)。体力に自信のない方は、ここに行っても展望台だけに留めた方がいいかもね。
それから海沿いの断崖上の、レンタカー屋のお姉さんに行くなと言われたワインディングロードを通って、富江町というところの珊瑚工房に寄ったが、お土産になるかもと思っていたものの、やっぱ珊瑚の製品は高いし、人もいなくて寂しい場所だったので、買うのはやめて宿に戻って来た。
てことで大変長くなりましたが、五島旅行2日目と3日目の記録でした。
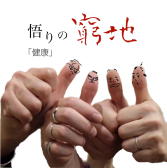


コメント